第27回日本医薬品情報学会総会・学術大会 一般演題(ポスター)発表について
会 期:2025年7月5日(土)、6日(日)
場 所:広島大学霞キャンパス
一般演題発表形式:ポスター発表
演 題:ジェネリック医薬品の電子添文から考える医薬品情報~新記載要領対応で生じた情報相違~
演 者:日本ジェネリック製薬協会 安全性委員会 電子添文検討部会
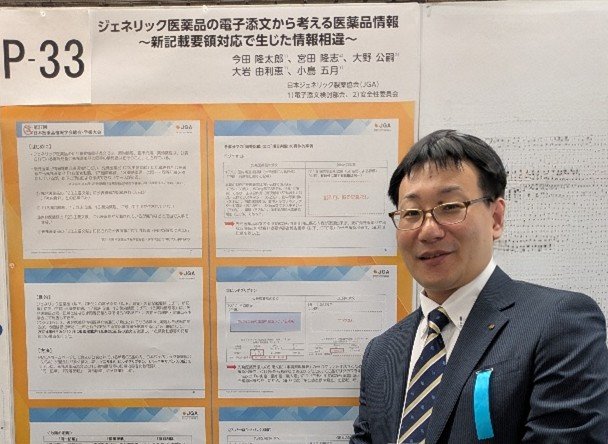
医療用医薬品の添付文書は、2023年8月1日より製品個装箱への紙媒体(紙面)文書の同梱添付から、個装箱に表示したGS1バーコード*読み取りによる電子的な情報提供方式に完全移行となり「電子添文(電子化された添付文書)」と呼称されるようになりました。また2024年4月1日をもって、全ての医療用医薬品の電子添文は「添付文書の新記載要領**」に基づく記載内容に完全移行しました。ジェネリック医薬品(以下、GE品)電子添文の新記載要領移行においては、医療従事者が当該医薬品を適正に使用する際に必要とされる情報が記載されている「16.薬物動態」「17.臨床成績」「18.薬効薬理」の各項について、公表されている資料(申請資料概要や審査報告書、学術文献等)により同一有効成分の先発医薬品と同等の情報を記載することが求められていますが、公表されている資料等の範囲の情報では同等の記載とはならない等、多くの問題に直面しています。この問題点については、医療用医薬品の使い手である医療従事者にその実態を広く認識していただくことが重要であると考え、GE薬協 安全性委員会は2022年の日本医薬品情報学会総会・学術大会(以後、JASDI学会)より、その問題点に関する情報発信を継続して実施して参りました。なお、同等記載問題の詳細につきましてはJGAニュース2024年5月(No.193)に掲載しておりますのでご参照ください。
今年のJASDI学会においては、現時点でも十分な問題解決に至っていない上記の同等記載問題について、情報発信を継続することを目的として、学会発表を行うことと致しました。今回はポスター発表形式で、発表内容としては2024年に初めてGE品が薬価収載となった3成分の電子添文の記載状況を調査した結果を報告させていただきました。調査対象としたのは①ゾニサミド(2024年6月初収載)、②ビルダグリプチン(2024年12月初収載)、③リバーロキサバン(2024年12月初収載)の3成分15品目です。いずれの品目においても先発医薬品との記載相違箇所が存在し、18.6%の箇所に記載相違が確認されました。具体的にどのような記載の相違が確認されたのかにつきましては、以下の通りです。
●先発医薬品の電子添文では記載されている臨床試験で確認された副作用情報(副作用名、発現頻度)の一部がGE品電子添文では記載されていない
●先発医薬品の電子添文では掲載されている単回投与時の血漿中濃度推移グラフがGE品電子添文では掲載されていない
●単回投与時の薬物動態パラメータの最高血中濃度(Tmax)の数値が異なる(先発医薬品は中央値、最小値、最大値に対し、GE品は平均値±標準偏差の記載のため)
●先発医薬品、GE品共に電子添文には「生物学的同等性(試験)」の項目があるが、それぞれ記載されている内容が異なる(先発医薬品が記載している生物学的同等性試験の目的はGE品とは異なるが、先発医薬品の生物学的同等性試験結果が公表されていないため記載内容が異なっている)
以上の結果は、これまでの調査・検討で明らかになっている相違事例の傾向と一致しておりました。
なお、今回調査対象としたGE品3成分15品目の同一有効成分における電子添文間の記載相違は確認されませんでした。これは同一有効成分のGE品において、電子添文の記載に相違があると医療従事者へ無用な誤解を与えることになるため、GE薬協が作成した「ジェネリック医薬品の電子化された添付文書作成の考え方-主に16.薬物動態、17.臨床成績、18.薬効薬理について-」も参考にしつつ、GE企業各社がこれまで蓄積してきた経験・知見を活かして各社が電子添文を作成しているためと考えられます。
今回の発表のまとめとしましては、
●今回調査対象とした3成分の先発医薬品は、2010年頃に承認された新医薬品であり、申請資料概要及び審査報告書(以下、CTD等)が公表されており、GE品の電子添文についても比較的同一・同等記載が可能な公表資料入手環境が整っていた時期と考えられた。
●逆に、先発医薬品の電子添文がCTD等や学術文献といった公表情報ではない情報(例えば非公表の社内資料等)に基づく記載が多い場合や、先発医薬品の承認申請情報の公表が限定されている時期の製品では同一・同等記載が困難な項目が多いことがこれまでの調査で明らかとなっている。
●電子添文は医薬品適正使用の基礎となる法的文書であるため、使用上の注意、取扱い上の注意のみならず、「16.薬物動態」「17.臨床成績」「18.薬効薬理」の項も含め、先発医薬品とGE品で同等記載ではなく、同一記載となることが重要と考える。
●更には、承継されることなく撤退する先発医薬品(長期収載品)が存在する昨今の状況を鑑みると、GE品電子添文の情報充実も含め、産官学で医薬品適正使用に必要な情報の適切な維持管理について議論する必要があると考える。
と述べさせていただきました。
ポスター発表は、聴講者にご参集いただく口頭発表に比べ情報発信としては少し力不足となる面がありますが、一方で口頭発表とは異なり発表時間制限が無いため、興味を持っていただいた方にはポスターをじっくりと見ていただけますし、質疑等もゆっくりと行えるという利点もありました。今回、演者がポスター付近に立ち説明する時間は45分間設けられており、薬局薬剤師、先発医薬品メーカー、GE品メーカー、業界関連団体の方等、さまざまな方がポスターをお読みいただき、また、多くの質疑応答や意見交換を行うことができました。一例として、「そもそもこういった情報相違があること自体を知らなかった」、「なぜ先発医薬品の電子添文と全く同じ記載にできないのか?」、「先発医薬品の電子添文を引用文献として同じ内容を記載することはできないのか?」、「先発医薬品のCTDには血漿中濃度グラフが記載されていないのか?」、「先発医薬品はCTDに載っていない数値情報をなぜ電子添文に記載するのか?」、「同じ有効成分の電子添文において記載されている数値が異なることには違和感があるが、記載根拠をしっかりと説明することが出来て、誤った数値でなければ情報提供した方が良いのではないか」、「先発医薬品が撤退する場合に、その情報が失われないようにするためには、具体的にどのような仕組みがあると良いのか?」といった忌憚の無いご意見を多数いただき、説明に熱が入ると共に、異なった視点を持たれた方たちとの意見交換に新鮮な刺激を受けました。特に「GEメーカーは電子添文の記載相違について問い合わせが来たら説明できるのか?」というご質問に対して、改めて自社の電子添文に対する説明責任と、コールセンター、MR等の社内関連部署との連携の重要性を感じました。
今回の発表を通じて、GE品電子添文と先発医薬品電子添文に情報相違がある実態については、医療現場での認知度はそれほど高くは無く、継続的な情報発信を行っていくことが重要であると感じました。更に、GE品電子添文に情報相違がある状態で先発医薬品が撤退してしまった場合には、医療現場から貴重な医薬品情報が喪失してしまうという危うい状況が身近に潜んでいることを、今後も訴えていかなければならないと感じました。
2025年3月末時点でGE品数量シェアは90%に到達する状況となって参りました。しかしながら、そのGE品の多くの電子添文に先発医薬品との情報相違や情報欠損があることは、当該医薬品を使用される医療従事者や、その患者さんに対して想定外の不利益をもたらしてしまう可能性もあると思われます。
同一成分では同一記載という電子添文の本来あるべき姿となることを理念として、引き続き行政当局との折衝、医療従事者の皆様への問題提起を行うなどの活動を継続して参ります。
*GS1バーコード:GS1識別コードとも称し、流通コードの管理及び流通標準に関する国際機関であるGS1が定めている国際標準の識別コード。医療用医薬品の個装箱等に記載されたGS1バーコードを専用のアプリで読み取ることにより最新の電子添文にアクセスできるシステムとなっている。
**添付文書の新記載要領:平成29年6月8日付け薬生発0608 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」により改正された記載要領で、医療用医薬品の添付文書への記載項目や記載順序、記載上の注意点等が具体的に示されている。医療やIT技術の進歩、高齢化率の上昇など、医療を取り巻く状況が大きく変化していることから、より理解し易く活用し易い内容の添付文書にすることを目的に約20年ぶりに改正が行われた。
参考情報:
1)JGAニュース No.193
https://www.jga.gr.jp/information/jga-news/2024/193.html



